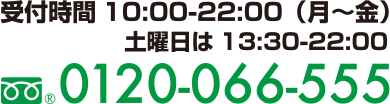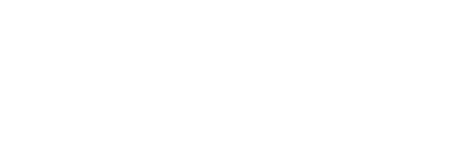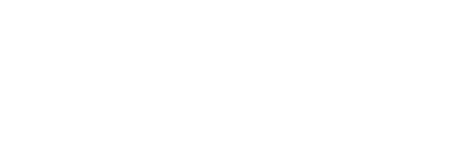開倫塾
2024年度版
県立高校入試問題分析
茨城県版
2024年度入試の出題傾向・2025年度入試へ向けて
1.2024年度入試の出題傾向
今年度の茨城県立高校入試はどの教科も出題傾向は概ね昨年と変わらない試験でした。記述式解答もありましたが、全体的には記号選択式解答が多かったように思います。大問数もほぼ例年通りでした。全体的には理系教科は平均的な難易度で、英語や社会は昨年よりも解答に苦労する問題が多かったかもしれません。また、各教科とも出題問題ごとの文字数が多く、理科・社会では大量の資料から必要な情報を抽出する思考力・判断力・分析力・情報処理能力が求められています。ですから日頃から問題演習量を豊富にし、様々な問題に慣れておくことが必要です。
まず教科書の学習内容を定着させましょう。音読練習や書取練習で知識を完全に定着させることで、問題を解く際の「土台」が出来上がります。茨城県公立高校入試の出題傾向は難問奇問ばかりが出題されるわけではなく、基礎基本をベースに作問されています。毎日の学習の積み重ねを意識して取り組んでいくと良いでしょう。
まず教科書の学習内容を定着させましょう。音読練習や書取練習で知識を完全に定着させることで、問題を解く際の「土台」が出来上がります。茨城県公立高校入試の出題傾向は難問奇問ばかりが出題されるわけではなく、基礎基本をベースに作問されています。毎日の学習の積み重ねを意識して取り組んでいくと良いでしょう。
2.2025年度入試へ向けて
茨城県の公立高校入試は教科書で学習した内容から出題されます。出題問題のレベルも基礎問題から応用問題までまんべんなく出題されています。ですから、日頃から基礎基本の反復学習に取り組み、教科書内容をきちんと定着させることが大切です。英語では「豊富な語彙力」が求められます。教科書で学習した英単語や構文は音読練習と書取練習を繰り返して定着させなくてはなりません。リスニング問題では日頃どれだけ英語を声に出していたかで得点力が変わってきます。ここでも音読練習が効果的です。計算練習は毎日取り組んでください。数学では計算問題以外でも計算をする場面が何度も出てきます。理科でも計算力が求められます。「正確且つ早く」を意識した計算練習を繰り返すことで「圧倒的計算力」を身に付けてください。しかしながら、問題に答える「基礎知識」は当然必要ですが、単に知識を「覚える」だけではなかなか得点には結びつきません。それらを基にして問題を解く実践力が必要になってきます。学習方法として日頃から「まとめ→ 演習→ 見直し・解き直し」のサイクルで学習に取り組む姿勢を身に付けていきましょう。
茨城県支部長 戸叶勝彦
2024年度 県立高校入試問題分析【国語】
| 大問数 | 4問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 宮田明子 |
入試問題分析と講評
今年度の入試は、問題の構成に変化があった。以前は大問4 でよく出題されていた内容が、大問1 に移動してきている。選択問題がほとんどで、作文の出題は今年度もなし。記述は多くても2 5 字と短いものにとどまった。記述のパターンは抜き出しが大半。1 問だけ自由記述があったが、それも答えがある程度限定されるものだった。
大問別分析
【大問1 言語事項・漢字の読み書きなど】
以前までは大問4 で主に出題されていた内容。漢字の読み書きや言語事項がメインだが、問題数が増え、内容も多彩になった。手紙の内容に関する自由記述が、語句指定、字数制限ありで出題された。問題自体はあまり難しくないと思われる。
【大問2 文学的文章】
文学的文章とその感想の交流からの出題で、昨年と変わらないパターン。問題は5問で、そのほとんどが選択式。記述は1 5 字以上2 0 字以内の抜き出しが1 問。
【大問3 説明的文章】
説明的文章とそれをまとめたノートの一部から出題。パターンは昨年と似ているが、今年は説明的文章が一つだけになっていた。記述は字数指定の抜き出しで出題。大問2 と同じく文章量が多いので、素早く正確に読むことが今後も必要。
【大問4 古典の文章】
古文、漢文の書き下し文、話し合いの内容から出題する形式。記述は、指定文字数で抜き出してから、始めの5 文字を答えさせるという内容だった。読み方を現代仮名遣いで答えさせる問題は、書かせるのではなく選択式で出題。漢文は返り点に関する問題が出されていた。
新傾向や注意すべき問題
言葉の意味を答えさせる問題など
2025年度入試への対策
まず、文章や資料を組み合わせた問題が多く出題されているので、早く正確に文章を読む練習が必要になってくる。合わせて、文法や言語事項などの知識も強化しておきたい。また、語彙力アップには、分からない言葉を辞書で調べることが有効だ。
2024年度 県立高校入試問題分析【社会】
| 大問数 | 4問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 山口秀孝 |
入試問題分析と講評
問題の構成は昨年度と変わらず、大問1 は地理、大問2 が歴史、大問3 が公民、大問4が三分野融合問題。どの大問でもグラフや表などの資料を読み取る問題が出題された。また、1 5 字以上2 5 字以内の記述問題が出題された。
大問別分析
【大問1 地理分野】
問題数は8 問。前半は世界地理、後半は日本地理からの出題。( 2 ) や( 7 ) は基本的な地理の知識を問う問題だが、それ以外の問題は資料を読み取る問題が出題された。難易度はそれほど高くないが、計算して正解を判断する問題があり、ふだんから資料にふれておくことが大切。
【大問2 歴史分野】
問題数は8 問。資料や写真を使った問題が多いのが特徴で、文化に関する問題が2問出題された。写真に関しては教科書や資料集に載っているもので、難易度はやや易しめ。前述した文字数指定の記述問題が出題されたが、学校のワークでも同じような問題があるので、難易度は高くない。
【大問3 公民分野】
問題数は6 問で昨年度より減少した。政治分野から2 問、経済分野から3 問、国際関係分野から1 問出題。難易度は普通。( 3 ) や( 6 ) は、より深い知識が求められる問題だった。
【大問4 三分野融合問題】
問題数は6 問。地理分野から2 問、歴史分野から2 問、公民分野から2 問出題。難易度はやや易しめ。( 2 ) や( 4 ) に関しては、難しそうに見えるが、資料に書かれている文の内容をしっかり読み取ることができれば、正解を導き出すことができる。
新傾向や注意すべき問題
昨年度は5 字以内の記述問題が出題されたが、今年度は15字以上25字以内と文字数が増加。今後は文字数が増えたり、記述問題が増えたりすることも考えられるので、ふだんの勉強から記述問題に慣れておくことが必要だと思われる。
2025年度入試への対策
地理、歴史、公民のどの分野においても、まずは基礎的な用語や知識を身に付けることが大切。ふだんから一問一答形式の問題を解くことがオススメ。地理分野では地図帳、歴史分野では資料集を見ながら勉強するとより効果的。基本的な知識が身に付いたら、その知識に関する様々な問題を解いてみると良い。また、文章で書かれている資料を読む場合は、そこで言われていることを深く読み取る練習をすることも必要である。
2024年度 県立高校入試問題分析【数学】
| 大問数 | 6問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 伊藤 修 |
入試問題分析と講評
大問数は変わらず, 各単元から出題された。採点ミス対策が続いているのか, 解答を選択させる問題が増えた。全体として難易度は易~ 標準。上位層では80点以上,最上位層では90点以上は得点しておきたい。
大問別分析
【大問1 計算・因数分解】
・基本的な計算問題と因数分解。因数分解は選択式。難易度は易。
【大問2 小問総合】
・解答が全問選択式になった。難易度は易~ 標準。
【大問3 平面図形】
・平行線, 相似を利用した問題。題意に合った図を描く力が必要。
・証明は選択と穴埋め。誘導されている通りに進めば問題ない。
・難易度は標準。
・証明は選択と穴埋め。誘導されている通りに進めば問題ない。
・難易度は標準。
【大問4 確率】
・題意を正確に読み取れるかがカギ。( 2 ) は① から② の流れの中で, 円周角の定理と関係があることに気づけるかどうかが問われた。
・難易度は標準。
・難易度は標準。
【大問5 関数】
・水槽の問題としてはよくある問題で, 問題文や会話文から必要な情報をきちんと拾える力が必要。
・難易度は標準。( 2 ) ② はやや難。
・難易度は標準。( 2 ) ② はやや難。
【大問6 空間図形】
・ねじれの関係や表面積, 体積を求める問題。基本的な知識を使える力が問われた。
・難易度は標準。( 2 ) ⑵ は難。
・難易度は標準。( 2 ) ⑵ は難。
新傾向や注意すべき問題
選択式の解答が増えたことで, 大学入試の共通テストにより近づいた形になった。長い文や会話文から必要な情報を拾い上げる力が求められる。
2025年度入試への対策
基本的知識と基礎計算力は必須。選択式になっても解答を求めることは変わらない。特異な問題はないので, 数多くの問題演習でいろいろな形の問題に触れることで対応はできる。最上位を狙うなら難問と言われるものも経験値にすること。
2024年度 県立高校入試問題分析【理科】
| 大問数 | 6問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 黒野幸亮 |
入試問題分析と講評
大問構成は昨年度と変わらず。計算問題が生物分野を除き出題され、一方で作図・記述問題はなかった。完答型問題に語句の記入( 4 つ) を求める問題が出題された。
大問別分析
各問題は基本的な知識を問う問題と考察問題の組み合わせになっている。大問ごとの分析内容は以下の通りである。
〔大問1 小問集合〕
各分野から4 択の記号問題が2 問ずつ計8 題出題された。
〔大問2 電磁誘導(中2物理)〕
電流計・電圧計の読み取りとオームの法則の理解を問う計算問題が出題された。
〔大問3 状態変化(中1化学)〕
融点・沸点から考える物質の三態を問う問題が出題された。計算問題はエタノールの密度と質量を求める形式で、表の数字に注視して解く必要がある。
〔大問4 人体の構造(中2生物)〕
記号問題のみの出題。心臓と肺の仕組みが中心に出題されており、教科書に載っている図や実験がそのまま問われる形になっている。
〔大問5 天体の動き(中3地学)〕
完答型問題が語句を答える形式で、地球の自転の一連の流れを覚えておく必要がある。計算問題は太陽の南中高度を求める問題で、中3Keyワークp146 にほぼ同様の問題が出題されている。
〔大問6 分野融合問題〕
ISS ( 国際宇宙センター) の話を通じて、月面での質量と重さ( 中1 物理)、湿度と水蒸気量( 中2 地学)、大陸・海洋プレートの動き( 中1 地学)、冬型の気圧配置( 中2 地学)から出題された。計算問題で水蒸気の質量を求める際、文中にあるISS 内部の容積と単位に注視する必要がある。
新傾向や注意すべき問題
計算問題が多く出題され、解答も記号形式から脱却しつつある。複雑な計算は見られなかったので、公式と使いどころを演習を重ねて身に付けていく必要がある。
2025年度入試への対策
記述・作図問題が今年は出題されなかったが、計算問題含め引き続き対策する必要がある。教科書に記載されている図や実験がそのまま載っているケースが多かったので、日頃の予習復習で教科書・ノートを読み込む大切さを改めて実感できる問題だった。
2024年度 県立高校入試問題分析【英語】
| 大問数 | 6問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 原田和明 |
入試問題分析と講評
大問2 が、英単語を書かせる問題から、適語を選択肢から選ばせる問題へと変更。その他若干の変更も見られたが、全体的な問題傾向は前年と同様であった。大問6 は前年同様、語句整序だが、難度は上がっている印象。全体的な難度は標準であった。
大問別分析
【大問1 リスニング】
・( 4 ) ① 前年と同じくイラストの並び替え問題だが、変更点として1 つ不要なイラストが入っている。
【大問2 適語補充】
・2 人の会話文の空所に前後の文脈に合うよう選択肢から英単語を選ぶ問題。built( 受け身)、learning ( 動名詞) 、could ( 仮定法) といった文法から、belong ( to ) ~ に所属する、( be ) famous ( for ) ~ で有名である、といったイディオムなどが出題された。
【大問3 長文読解】
・( 1 ) 中学生のスピーチを読んで要旨を把握する問題。
・( 2 ) 英文の空所に3 つの文を並びかえる文整序の問題。
・( 2 ) 英文の空所に3 つの文を並びかえる文整序の問題。
【大問4 対話文】
・( 1 ) 学校の「図書館便り」を見ながら話をしている2 人の対話文を読んで、空所に適切な語句や文を選択肢から選ぶ問題。
・( 2 ) 対話の流れに合うように空所に適切な英語を入れる適語句補充の問題。
・( 2 ) 対話の流れに合うように空所に適切な英語を入れる適語句補充の問題。
【大問5 長文読解】物語
・( 4 )、( 5 ) の問題の順番は異なるが、それ以外は前年と同じ傾向。( 5 ) が書き抜きから英作文の形に変更されている。
【大問6 語句整序】
・不要な語( 句) を一つ除いて並びかえる問題。
新傾向や注意すべき問題
大問2 は英単語を書かせる問題から選択問題へと変更された。記号を選ぶ問題ではあるが、しっかりとした文法力および語彙力が無いと正答できない。一長一短で身につけられないので、日々のたゆまぬ練習が求められる。
2025年度入試への対策
今年も大問6において自由英作文ではなく、語句整序が出題された。難度は高く、文法力だけでなく正しい文の形を身につけることが求められるので、英作文の練習は必須である。また毎年出題されているリスニング問題は30点を占める。確実に得点するためにも日々、英語の発音に耳を慣らすことが大切である。