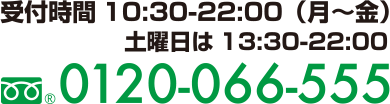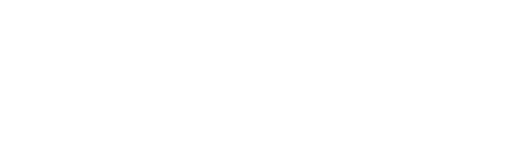開倫塾
2024年度版
県立高校入試問題分析
群馬県版
2024年度入試の出題傾向・2025年度入試へ向けて
1.2024年度入試の出題傾向
2024 年度の群馬県公立入試問題は、出題内容や形式に少しの変化はありましたが、ほぼ例年通りの問題の内容だったと思います。何問かは、難しいと感じる問題もありましたが、ほぼ全体的に、基礎的な知識を押さえておけば解ける問題だったと言えます。
各教科とも記述式の問題はありました。それほど多くないとはいえ、普段からしっかりと対策をしておかないと、難しく感じたと思います。特に社会科などは、記述の他に、資料や表の読み取りの問題も出題されています。このような出題傾向はこれからも続いていくと思います。
近年の大学入試は、思考力や表現力を問う出題傾向となっており、高校入試もその傾向になりつつあります。単に知識が問われるだけでなく、文章の読み取りがただしくできるか、語句の意味をきちんと理解できているか、資料の分析ができるか、また、出来事や事象の背景や原因をちんと説明できるかなどの、総合的な学力が求められています。ただ、その総合的な学力とは、あくまでも基礎学力の延長線上にあるものだという認識です。基礎と総合力とは別のものではなく、基礎の積み重ねこそが総合力や応用力育成へとつながっていくものと思います。そういう観点から、群馬の入試問題は作問されていると言えるでしょう。
各教科とも記述式の問題はありました。それほど多くないとはいえ、普段からしっかりと対策をしておかないと、難しく感じたと思います。特に社会科などは、記述の他に、資料や表の読み取りの問題も出題されています。このような出題傾向はこれからも続いていくと思います。
近年の大学入試は、思考力や表現力を問う出題傾向となっており、高校入試もその傾向になりつつあります。単に知識が問われるだけでなく、文章の読み取りがただしくできるか、語句の意味をきちんと理解できているか、資料の分析ができるか、また、出来事や事象の背景や原因をちんと説明できるかなどの、総合的な学力が求められています。ただ、その総合的な学力とは、あくまでも基礎学力の延長線上にあるものだという認識です。基礎と総合力とは別のものではなく、基礎の積み重ねこそが総合力や応用力育成へとつながっていくものと思います。そういう観点から、群馬の入試問題は作問されていると言えるでしょう。
2.2025年度入試へ向けて
まず、学校の授業をきちんと受け、復習や予習をしっかり行う学習習慣をつけていきましょう。そのうえで、塾の授業を利用し、学習している単元や分野の根本的な理解をできるように意識していきましょう。上っ面のみの浅い知識では、資料の読み取りや事象の背景を説明するような記述の問題に対しては、手も足も出なくなってしまいます。
定期テストや実力テスト、開倫塾の模擬試験に向けての勉強や、テスト後の見直し勉強を良いペースメーカーにして、勉強してからテストに臨む、そして、テスト後の間違い直し勉強も十分に行うという学習方法をとれば、必ず学力はついていきますし、テストに強い体質になっていきます。くれぐれも、学校のワークの答えだけをみて、書き写すだけの浅い勉強に陥らないように意識をしていってほしいと思います。
「なぜ、こういう解答になるのか」「自分は何が足りなくてこの問題が解けなかったのか」など、そのような問題意識を持ちながら勉強していけば、どのような角度から入試問題が出ても、必ず正解を導くことが可能になります。塾では、入試が間近になると、過去問演習を行います。試験に出題されそうなところを学習するというのも一つの方法ですが、どんな問題が出ても、必ず解けるという学力をつける意識を持つことが大切です。今のうちからその意識で勉強していきましょう。
開倫塾は学習方法に音読を取り入れることを強く勧めています。これはどの教科にも当てはまります。学習においては面倒くさがらずに、先生の指導を素直に実行していくことが、入試突破のカギを握っているのです。
定期テストや実力テスト、開倫塾の模擬試験に向けての勉強や、テスト後の見直し勉強を良いペースメーカーにして、勉強してからテストに臨む、そして、テスト後の間違い直し勉強も十分に行うという学習方法をとれば、必ず学力はついていきますし、テストに強い体質になっていきます。くれぐれも、学校のワークの答えだけをみて、書き写すだけの浅い勉強に陥らないように意識をしていってほしいと思います。
「なぜ、こういう解答になるのか」「自分は何が足りなくてこの問題が解けなかったのか」など、そのような問題意識を持ちながら勉強していけば、どのような角度から入試問題が出ても、必ず正解を導くことが可能になります。塾では、入試が間近になると、過去問演習を行います。試験に出題されそうなところを学習するというのも一つの方法ですが、どんな問題が出ても、必ず解けるという学力をつける意識を持つことが大切です。今のうちからその意識で勉強していきましょう。
開倫塾は学習方法に音読を取り入れることを強く勧めています。これはどの教科にも当てはまります。学習においては面倒くさがらずに、先生の指導を素直に実行していくことが、入試突破のカギを握っているのです。
群馬県支部長 津久井一則
2024年度 県立高校入試問題分析【国語】
| 大問数 | 5問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 熊谷 健 |
入試問題分析と講評
大問は漢文が削られ、5 題になった。出題形式も資料を使った意見交換の問題が大問4 に移り、小問数も2 0 題になったことで、より深く文章を読み込めるようになった。しかし、記号選択14題のうち半数以上が内容を把握していなければ解けない問題なので、問題数が減っても、読み取りに時間がかかる問題だと言える。
大問別分析
1.〈説明文〉
(市橋伯一「増えるものたちの進化生物学」による)
(更科功「若い読者に贈る美しい生物学講義ー感動する生命のはなし」による)
小問6 題( 選択4 題、記述2 題) は昨年より1 題多い。記述問題は例年通り抜き出し1題、字数制限なしの記述1 題。選択問題では今年も適切なものを「全て選ぶ」問いが出題された。また、2つの文章を参考に解く問題だったが、字数も約2350字と例年より500字以上多かった。
(更科功「若い読者に贈る美しい生物学講義ー感動する生命のはなし」による)
小問6 題( 選択4 題、記述2 題) は昨年より1 題多い。記述問題は例年通り抜き出し1題、字数制限なしの記述1 題。選択問題では今年も適切なものを「全て選ぶ」問いが出題された。また、2つの文章を参考に解く問題だったが、字数も約2350字と例年より500字以上多かった。
2.〈小説文〉
(辻村深月「この夏の星を見る」による)
小問4 題( 選択3 題、記述1 題) は昨年と変わらず。慣用表現の選択問題が出題されたが、語彙力を問う問題が昨年同様に出題された。また、小説文でも適切なものを「全て選ぶ」問いが出題された。記述問題は字数制限がない上に、文中の言葉・表現から読み取ったことを解釈し、自分の言葉でまとめ直すもので、かなりの時間をかけて練習する必要がある。
小問4 題( 選択3 題、記述1 題) は昨年と変わらず。慣用表現の選択問題が出題されたが、語彙力を問う問題が昨年同様に出題された。また、小説文でも適切なものを「全て選ぶ」問いが出題された。記述問題は字数制限がない上に、文中の言葉・表現から読み取ったことを解釈し、自分の言葉でまとめ直すもので、かなりの時間をかけて練習する必要がある。
3.〈古文〉(「大和物語」による)
小問6 題( 選択4 題、記述2 題) と昨年より2 題増えた。会話文と文章( 古文) を組み合わせた形式で、現代仮名遣いに加え、内容把握の問題が出題された。教科書レベルの古語の意味をしっかりとおさえ、会話文を参考に解けるようにしておく必要がある。
4.〈資料〉
(海外に伝えたい日本の魅力)
小問3 題( 選択2 題、作文1 題) は昨年同様。会話文と資料を、正確に読み取る力が問われる問いだが、会話の流れと発言者の意図をつかむことに集中しなければならない。また、作文は「食文化」「伝統文化」「歴史文化」から選び、選んだ理由を経験を踏まえて書くものだった。現代の学生が「自分の経験を踏まえて」作文を書くには、あらゆる面で経験不足と言える。
小問3 題( 選択2 題、作文1 題) は昨年同様。会話文と資料を、正確に読み取る力が問われる問いだが、会話の流れと発言者の意図をつかむことに集中しなければならない。また、作文は「食文化」「伝統文化」「歴史文化」から選び、選んだ理由を経験を踏まえて書くものだった。現代の学生が「自分の経験を踏まえて」作文を書くには、あらゆる面で経験不足と言える。
5.〈言語事項・漢文〉
小問3 題は昨年と同様。ただし、大問で漢文の出題がなくなった分、漢文の「返り点」の出題があった。漢字の読み書きは例年通り、書きは小学6 年生までに習う漢字、読みは中学3 年生までに習う漢検準2 級レベルのものが出題された。
新傾向や注意すべき問題
意見交換や会話文を多く取り入れているあたり、近年の教科書や学校授業に合わせた傾向といえる。現代文の長文記述は8点~10点の配点とかなり高めな上、ほぼ自分の言葉でまとめなければならないので、文章を正確に解釈できなければ、大幅に得点を落とすことになるだろう。
2025年度入試への対策
群馬県入試の前期後期が一本化され、入試の時期も早まった分、早期に読解力・記述力を仕上げる必要がある。日頃から新聞の記事やコラムなどを、自分の言葉でまとめる練習が最適である。また、現代文や古文の経験値を増やすために、国語の教科書を繰り返し読むこと、読解問題集を3回はくり返し解くとよいだろう。
2024年度 県立高校入試問題分析【社会】
| 大問数 | 7問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 羽鳥正彦 |
入試問題分析と講評
大問数・小問数などは昨年度までとほぼ同様。図などを正しく読み取る力や, 読み取った内容を簡潔に述べる力が試された。記号問題( 2 0 問) 正誤判断や語句の組み合わせなどの複雑な問題が多くなってきた。記述問題( 5 問) ほぼ一問一答形式の出題で, 難易度は低めだった。論述問題( 1 0 問) 短文2 問, 中文4 問, 長文4 問。問題の意図に沿った解答が求められた。
大問別分析
1 【総合問題】
沖縄がテーマ。( 4 ) の資料の読み取り問題は, Y の文章を正しく読み取る力が問われた。( 5 ) は難問。レポートや資料中のヒントから,「伝統文化をもとに, 新しいものを創造する」という内容の解答を導き出せたか。
2 【日本地理】
近畿地方より出題。( 1 ) 近畿地方で横断の断面図は珍しいが, 丹波高地や紀伊山地などの基本的な地形を覚えていれば難なく解けた。( 2 ) や( 3 ) は標準的。( 4 ) ② 資料が読み取りやすいので, 長文の論述問題としては簡単な問題といえる。
3 【世界地理】
アジア州より出題。( 4 ) の資料は読み取りやすいが, 解答では平均賃金の差と進出している日本企業数の推移の両方について述べなければならない。簡潔かつ正確に述べるにはある程度のトレーニングが必要であろう。
4 【歴史前半】
古墳時代から江戸時代にかけての生活や文化に関する出題。( 2 ) 遣唐使停止の理由を述べる問題。教科書に記載はあるが, 問題集等で触れられることも少ないため, 難しいと感じた受験生は多かったかもしれない。
5 【歴史後半】
明治時代から昭和時代にかけての人物に関する出題。2024 年から使われる新紙幣から渋沢栄一が登場。( 2 ) の資料は見慣れないものかもしれないが, 内容をよく読めば解答を導き出せる。
6 【経済分野】
( 2 ) の図式の読み取り, ( 5 ) の「効率」に関する論述が難しい。前者は文章や図式の意味を理解できるか, 後者はどのように論述するかが問われた。
7 【政治分野】
( 1 ) , ( 2 ) , ( 3 ) は比較的簡単。( 4 ) の論述は定期テストや模擬テストで頻出の問題なので解きやすい。( 5 ) は衆参両院について触れることがポイントである。
新傾向や注意すべき問題
▼ 初見の資料や図表を, これまでに学んだ知識と関連づけて解答を導き出すような問題など, 大学入試共通テストに近い出題傾向が見られた。▼ 全体的な出題数が以前よりも少なくなっており, その分論述問題の配点が以前よりも高くなっていると考えられる。
2025年度入試への対策
① 基本に立ち返って, 教科書本文はもちろん, 写真や資料,章と章の間の読み物まで読み込もう。② 一問一答の問題集などで知識を正しく蓄えよう。③ テスト問題などの解きなおしに力を入れよう。記号問題ならば「なぜこれが正解なのか」「なぜこれが誤りなのか」などを分析できるとよい。④ 高得点を狙うならば論述問題の攻略が必須。これまで以上に作文力が問われる。
2024年度 県立高校入試問題分析【数学】
| 大問数 | 5問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 石川直美 |
入試問題分析と講評
昨年より大問が1 問減り5 問になった。試験時間が今まで60分が多かったが50分になり、読み取る文章が多くなったため、問題量は昨年と同様であると思われる。大問3 にコンピュータを使った図形の問題が会話形式で出題された。データの分析が大問4 で出題され、昨年よりも配点が多くなった。大問1 は昨年までと同様であり、大問3 以降は大学共通テストのような読解力が必要な問題に大きく変わった。
大問別分析
【大問1 】昨年までと同様、小問集合9問
難易度も例年通り高くない。( 9 ) の2 次関数は自動車の制動距離の問題で読み取りにくい受験生もいたかもしれない。2 次関数の問題はこの問題だけだった。
【大問2 】不等式と連立方程式の問題
連立方程式は例年よく見られる内容であり、不等式とともに立式しやすい。途中の過程を記述する方法も近年多い形式である。
【大問3 】図形の証明と作図の問題
コンピュータを使った図形の性質についての会話文があった。会話文を読まなくても問題を解くことができるが、会話は今まで出題されていないので難易度が高く感じる。昨年まで証明は合同か相似だったが、面積が等しいことを証明する問題だったので、解きなれていないことで得点できなかった受験生もいたと考えられる。( 2 ) の作図と作図の理由を説明する問題は円周角を利用したもので、難易度が高かった。作図の理由を記述する問題は2 0 2 1 年にも出題されている。
【大問4 】データの分析(箱ひげ図、ヒストグラム)の問題
3問出題され、すべて選択問題である。難易度は高くない。データの分析は昨年までは大問1の小問集合に1問だけ出題されていたので、今年は配点が多くなった。
【大問5 】1次関数、相似、1次方程式の問題
山登りの歩く距離の問題であり、文章が多く、読解力が必要である。( 1 ) は相似比を利用する問題で難易度は高くない。( 2 ) は基本の速さを求めないまま距離を求める問題なので、立式することが難しいと感じられる。しかし昨年までの大問6 にあったような面積を求める問題や動点の問題と比較すると偏差値上位の受験生にとっては難易度が低いと考えられる。
新傾向や注意すべき問題
大問3 以降は大幅に傾向が変わり、大学共通テストのように読解力が必要になった。内容を理解できれば立式や計算は難しくない問題になった。データの分析が大問1 問分出題され、配点が多くなった。大問3 が会話形式であり、合同と相似以外の証明問題が出題された。昨年まで多かった図形の問題( 三平方・相似など) がほとんど出題されなかった。
2025年度入試への対策
傾向が大きく変わったものの、大問1の小問集合約40点は昨年までと同様なので、基礎をしっかり反復練習させる。データの分析も重点的に学習させる。全国の入試問題の過去問演習を行い、会話形式や複数単元の融合問題に慣れさせる。傾向は常に変わるという意識で学習させる。
2024年度 県立高校入試問題分析【理科】
| 大問数 | 5問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 大橋貴子 |
入試問題分析と講評
出題の形式, 難易度ともにほぼ例年通りであった。大問2 以降はすべての問題に, 会話文があり, 問題の文章が長くなっている。問題中の実験内容, 実験結果の意味をきちんと理解して解く力が必要だが, 基本的な問題も多く出題されているので, まずは基礎知識をしっかりつけることが大切である。その上で, 会話文の多い問題を演習し慣れていくことが必要だ。
大問別分析
大問1 小問集合
[ A ヒトの体のつくりとはたらきB 天気C 還元D 電力]
※ いずれも基本事項の出題である。
※ いずれも基本事項の出題である。
大問2 生物分野
[ 生物の進化と多様性( 中3 範囲)]
( 1 ) 脊椎動物の進化( 2 ) 哺乳類のからだのつくり
※ 全て基本問題であり, かなり難易度は低い。
( 1 ) 脊椎動物の進化( 2 ) 哺乳類のからだのつくり
※ 全て基本問題であり, かなり難易度は低い。
大問3 地学分野
[ プレートの動き( 中1 範囲)]
( 1 ) しゅう曲, 断層のでき方( 2 ) 地面の沈降と隆起の起こる周期
※ 会話文の誘導に従い, グラフから数値を読み取り考える問題。難易度は高くないが, データを読み取る力が必要。
( 1 ) しゅう曲, 断層のでき方( 2 ) 地面の沈降と隆起の起こる周期
※ 会話文の誘導に従い, グラフから数値を読み取り考える問題。難易度は高くないが, データを読み取る力が必要。
大問4 化学分野
[ 水溶液とイオン( 中3 範囲)]
( 1 ) 塩酸と水酸化ナトリウムの中和( 2 ) 中和とイオン
※ 中和が起こっているときの水溶液中のイオンの数, 化学反応式など頻出の問題が出題されていた。全体の難易度は高くないが結果から考察する力も若干必要。
( 1 ) 塩酸と水酸化ナトリウムの中和( 2 ) 中和とイオン
※ 中和が起こっているときの水溶液中のイオンの数, 化学反応式など頻出の問題が出題されていた。全体の難易度は高くないが結果から考察する力も若干必要。
大問5 物理分野
[ 凸レンズによる像のでき方( 中1 範囲)
( 1 ) 光の進み方( 2 ) 焦点距離と像の大きさ( 3 ) 光の進み方と像のできる位置
※ 凸レンズの作図等, 基本的な問題が多く, 難易度は高くない。
( 1 ) 光の進み方( 2 ) 焦点距離と像の大きさ( 3 ) 光の進み方と像のできる位置
※ 凸レンズの作図等, 基本的な問題が多く, 難易度は高くない。
新傾向や注意すべき問題
特に新傾向や特筆すべき問題はなかった。ここ数年の流れ通りの問題であった。
2025年度入試への対策
基礎的な問題が大半を占めているため, 用語をしっかり覚えたり, 公式にあてはめて計算をする練習等が大切。会話文が多いため, 問題文の分量が多くなるので問題を解くうえでヒントになるもの, 必要な数値等を素早く見つける練習も必要。
2024年度 県立高校入試問題分析【英語】
| 大問数 | 7問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 津久井一則 |
入試問題分析と講評
昨年度の入試と大きく変わった点はありません。単語や文法に関する問題や, 対話文, 長文問題の内容把握, そして字数指定の英
作文問題など, 基礎力がしっかりとついているかを問う問題が出題されています。
大問5 番の対話文と, 6 番の長文問題の英文が少し長めなので, 普段から長文を読み込んでいないと, 時間内に終わらせることが難しいと言えます。
作文問題など, 基礎力がしっかりとついているかを問う問題が出題されています。
大問5 番の対話文と, 6 番の長文問題の英文が少し長めなので, 普段から長文を読み込んでいないと, 時間内に終わらせることが難しいと言えます。
大問別分析
1 リスニング
適切なイラストを選んだり、絵の内容を理解しているかを問う問題。少し長めのアナウンスの英文を聞いて、記号で答える問題と、英文で答える問題。1 番だけは、今年度から1 度読みになりました。
2 リスニング
会話の最後に適する英文を選ぶ問題が2 題と、発表された英文を聞いて、空欄を埋めるための適切な英文を選ぶ問題が3 題出題されました。
3 会話文
会話の流れに合う疑問文や質問に対する答えの文を作る問題です。
4 動詞挿入問題
原形や動名詞、過去分詞など、時制や表現によって動詞を正しい形にして挿入できるかが問われています。teach を過去分詞にする問題と、現在完了でtriedを入れる問題も難しかったかもしれません。
5 対話文
今年から新紙幣が発行されることにちなんで、様々な国の紙幣にまつわるエピソードを、ホームステイをしているイギリス人の少女を交えて話している対話文です。今年は適文選択の問題が去年より1 題増えました。
6 長文読解
「自分が影響を受けた人」について授業で発表した内容についての英文を解釈し、設問に答えます。英問英答の出題が例年通り2題、内容一致の文を選ぶ問題が1 題、5 語~10語程度の英語を書いて、空欄を埋める問題が2題出ました。
7 自由英作文
「睡眠」についてのアンケートを読んで、worksheet の空欄を英語で埋める問題です。グラフの読み取りについて1 0 ~ 1 5 語で答える問題と、良い睡眠を得るためにはどうすればよいかを20~30語で書く問題の2 題出題されました。
新傾向や注意すべき問題
7番の英作文問題が難しいでしょう。その場で考えて答えられるような問題ではありません。普段から、基本例文の暗記と、問われているトピックに対して、暗記した英文をアレンジして書いていくという作業を身につけておくべきでしょう。
2025年度入試への対策
群馬県の公立入試は、3 ~ 4 年に出題形式を変えてきます。この形式になって4 年が経ちました。もしかしたら、来年度は3 番か4 番で出題形式の変更があるかもしれません。ただ、英語学習の基本は、あくまでも基本例文の暗記と、長文の音読です。これらを粘り強く継続していくことが、入試英語の対策になります。塾では、入試テクニックは教えますが、基礎力( 単語力・基本文の暗記) がついていない人は、テクニックを使いこなすことができません。まずは、コツコツと暗記の勉強をやっていってほしいと思います。