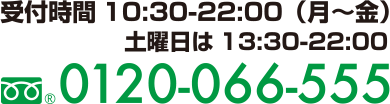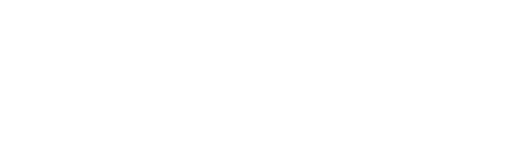開倫塾
2024年度版
県立高校入試問題分析
栃木県版
2024年度入試の出題傾向・2025年度入試へ向けて
1.2024年度入試の出題傾向
学習指導要領を踏まえて、基礎的な知識から文章や資料の読解力・分析・考察力、記述表現力を試す問題までバランスよく出題された。5 教科全体として難度は例年通りか、やや難化と言ったところ。近年は、「思考力・判断力・表現力」にウェイトを置く出題が増加傾向にあるが、今年度もそれぞれの教科でその傾向が見られた。
国語は大問構成が大きく変更され、読解・記述問題への配点が増加、設問中の会話文をあわせると問題文の文章量も増加している。社会や理科は、資料や図表から解答に必要な情報を正確に読みとり、考察させる問題が多く、情報処理能力が問われた。数学では最後の大問6 で、修学旅行という身近な場面を題材に長文が提示された。制限時間内に情報を整理・理解して対応する数学的思考処理能力が求められる問題であった。英語では、問題構成が変更されたものの、複数の長文問題や英作文の問題が変わらず出題されている。基礎的な語彙力・文法力とともに速読力、要点把握力、表現力が試された。
昨今、AI 技術の発展など社会状況の急速な変化が取りざたされている。それらを受け、教育内容は子どもたちが社会に出たときに要求される力が身につけられるよう見直され続けており、2020 年の教育改革以降、学習指導要領の改訂、大学入試制度改革などがなされ、高校入試にもそれらが反映されている。したがって、冒頭の傾向は今後も続くと思われる。
国語は大問構成が大きく変更され、読解・記述問題への配点が増加、設問中の会話文をあわせると問題文の文章量も増加している。社会や理科は、資料や図表から解答に必要な情報を正確に読みとり、考察させる問題が多く、情報処理能力が問われた。数学では最後の大問6 で、修学旅行という身近な場面を題材に長文が提示された。制限時間内に情報を整理・理解して対応する数学的思考処理能力が求められる問題であった。英語では、問題構成が変更されたものの、複数の長文問題や英作文の問題が変わらず出題されている。基礎的な語彙力・文法力とともに速読力、要点把握力、表現力が試された。
昨今、AI 技術の発展など社会状況の急速な変化が取りざたされている。それらを受け、教育内容は子どもたちが社会に出たときに要求される力が身につけられるよう見直され続けており、2020 年の教育改革以降、学習指導要領の改訂、大学入試制度改革などがなされ、高校入試にもそれらが反映されている。したがって、冒頭の傾向は今後も続くと思われる。
2.2025年度入試へ向けて
上述の通り、高校入試はさまざまな単元・分野からバランスよく出題される。模擬テストなどで苦手を洗い出し、その弱点を克服することが得点を安定させる近道である。そのためにも、定期的に実施される開倫模試を最大限活用して自身の客観的分析・補強をくり返してほしい。
また、テストには基礎から応用まで幅広い難度の問題が出題される。応用問題を間違えた場合、「これが入試に出たら・・・・・・」と不安になり、「何とか解けるようにしなくては」と焦るのは自然な心理である。しかし、入試は基本~ 標準レベルの問題が中心。最優先で取り組むべきは、それらの問題に確実に正解できる基礎力を固めることである。なお、必ずしも「基礎・基本」= 簡単とは限らない。「基礎・基本」とは、「学習の土台」となる内容のことであり、疎かにすると必ず痛い目を見る。一方、基礎を徹底した生徒は後半の伸びが明らかに異なる。盤石に固めた土台があるからこそ、その上に「高得点」が成立するのである。毎回の確認テストや定期テストに真剣に取り組むこと。こうして築き上げた差は、ライバルたちにも一朝一夕に覆せない大きな差となるはずだ。
基礎を前提として、「思考力・判断力・表現力」を磨くためのポイントのすべては毎回の授業の中にある。語句の暗記に満足せず、普段から「根本的意味」・「なぜそう解くのか」を理解し、「自ら深く思考」し、「自身の考えを正確にまとめる」練習を怠らないこと。開倫塾の入試対策や各講習・特訓では、そうした実践的指導を中心に行う。先生のひとつひとつの言葉を大切に入試を乗り越えよう。
また、テストには基礎から応用まで幅広い難度の問題が出題される。応用問題を間違えた場合、「これが入試に出たら・・・・・・」と不安になり、「何とか解けるようにしなくては」と焦るのは自然な心理である。しかし、入試は基本~ 標準レベルの問題が中心。最優先で取り組むべきは、それらの問題に確実に正解できる基礎力を固めることである。なお、必ずしも「基礎・基本」= 簡単とは限らない。「基礎・基本」とは、「学習の土台」となる内容のことであり、疎かにすると必ず痛い目を見る。一方、基礎を徹底した生徒は後半の伸びが明らかに異なる。盤石に固めた土台があるからこそ、その上に「高得点」が成立するのである。毎回の確認テストや定期テストに真剣に取り組むこと。こうして築き上げた差は、ライバルたちにも一朝一夕に覆せない大きな差となるはずだ。
基礎を前提として、「思考力・判断力・表現力」を磨くためのポイントのすべては毎回の授業の中にある。語句の暗記に満足せず、普段から「根本的意味」・「なぜそう解くのか」を理解し、「自ら深く思考」し、「自身の考えを正確にまとめる」練習を怠らないこと。開倫塾の入試対策や各講習・特訓では、そうした実践的指導を中心に行う。先生のひとつひとつの言葉を大切に入試を乗り越えよう。
栃木県支部長 磯貝直希
2024年度 県立高校入試問題分析【国語】
| 大問数 | 5問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 小島繁美 |
入試問題分析と講評
大問構成に大きな変化がありました。大問1 は漢字の読み書き各5 問となり、語句の知識等の問題は大問5 に移動して各2 点の1 0 点の出題となりました。大問2 は論説文、大問3 は小説文、大問4 は古文、大問5は語句の知識等と作文と大きな変化がありました。作文の配点が従来の2 0 点から1 2 点となり、その分の配点が古文に4 点、論説文・小説文に各2 点割り振られています。
大問別分析
【大問1 : 漢字の読み書き】
漢字の読み書き各2 点で1 0 点。
全体的に大幅な問題構成の変化があったためか、漢字の読み書きは難易度は低めでした。
全体的に大幅な問題構成の変化があったためか、漢字の読み書きは難易度は低めでした。
【大問2 : 論説文】
論説文に変更。文字数は約1 9 0 0 字と昨年とあまり変わりません。
配点が2 2 点分となり記述問題が4 5 字以内で6 点という高い配点のものがありました。また記号で答える問題であっても2 点・3 点・4 点と様々であり、各問の難易度に細かく合わされました。
配点が2 2 点分となり記述問題が4 5 字以内で6 点という高い配点のものがありました。また記号で答える問題であっても2 点・3 点・4 点と様々であり、各問の難易度に細かく合わされました。
【大問3 : 小説文】
小説文に変更。文字数は2 ページ分あり、会話による改行もありますが2 7 0 0 文字程度と昨年より文字数が増えました。そのためか問題数は昨年の6問から5 問に変更されて、6 点の記述問題( 6 5 字以内)、5 点の記述問題( 4 0 字以内)と高い配点がみられ、記号問題も3 点か4 点と高めな配点となりました。
【大問4 : 古文】
古文に変更。文字数は4 5 0 字と昨年より少なめではありますが、1 4 点分と例年より4 点増え、4 点の記述( 2 0 字以内) も見られました。また3 0 0 字程度の「この古文を読んだ生徒の会話」があり、それを読んで答える問題が4 点・3 点と計7 点分あり、実質大問4 での読解量は増えています。
【大問5 : 文法・語句・作文等】
「環境問題解決のために」というテーマでポスター作成を行っているグループの会話の一部を読んで各問に答える形式。語句の構成2 点・品詞名2 点・対話文内の俳句に関する出題2 点・会話文の読解等2 点× 2 問となっています。作文は2 0 0 字以上2 4 0字以内の字数制限は昨年同様ですが、配点が1 2 点と大幅に減少。条件は、自然環境保護の啓発ポスター2 候補から1 つを選び、その理由を明確にするというものでした。
新傾向や注意すべき問題
作文の配点が減り、記述式解答の配点が多くなりました。また、小説文の文章量が増え問題の配点も増えました。漢字の読み書きや文法・語句の問題以外は全体的に難易度は高めになっています。
2025年度入試への対策
文章を読む機会をさらに多くし、長めの記述問題に対応できる読解力と記述力を育成することを必達目標として学習計画を立てる必要があるでしょう。基礎・基本的な国語の力は1 , 2 年までに育成し、さらに3 年生の受験対策として読解力の応用・記述力の完成を目指しましょう。
2024年度 県立高校入試問題分析【社会】
| 大問数 | 6問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 前原圭太 |
入試問題分析と講評
大問数、配点ともに昨年と変化なし。地理の論述問題において、純粋に資料を読みとれば、得点可能な問題が出題された。昨年同様、公民においてS D G s に関する問題が出題されるなど、単なる知識の詰め込みでない、問題解決能力が問われ始め、難易度が上がってきている印象を受ける。
大問別分析
【大問1 】日本地理
気候に関する問題で雨温図の表記がなかった。地形図と断面図の問題に関しては、標準的な問題だった。
【大問2 】世界地理
資料の正確な読み取りが求められ、かつ会話文中に入れて不自然でない表記で論述する必要があるなど、国語力も試されている印象を受ける。
【大問3 】古代~ 近世史
歴史年表なし。貿易( 勘合貿易) に関する問題が、輸出入品を細かく暗記している必要があり、若干難易度が高め。全体的に産業( 経済) 史、文化史に傾倒していた印象。
【大問4 】近現代史
昨年に引き続き、産業( 経済) 、文化に関する問題が必ず出題されている。資料を読み取ったうえで、まとめの文に合うような論述をする問題が出され、こちらも国語力が求められているように思える。
【大問5 】政治・経済
昨年と同様に、政治と経済の両分野から大問にまとめて出題。税制度に関しての長所と短所を選択させたり、国連安全保障理事会の決定について、資料から正しい結果を選択させたりするなど、語句暗記だけでは対応が難しい問題が多い。
【大問6 】経済、現代と国際社会
昨年に引き続き、現代社会や国際社会への関心を問われる形式の問題が増えている。他の分野の論述と併せて、適性検査( 中高一貫で出されるような) 的な問題が多くなっていると思われる。
新傾向や注意すべき問題
地歴公民ともに、知識事項の定着だけでなく、正しい読み取りや、論述をする必要がある問題が増えている傾向にある。殊更、S D G s に関する問題などは、昨年に引き続いての出題になるなど、問題解決意識を図るための定番問題となっていくのではないか。
2025年度入試への対策
公民分野に関しては、しっかりと時間をとって現代社会、国際社会の分野に対する対策が必要になってくると思われる。地歴分野においては、語句暗記だけでなく、論述問題への対策も十分必要になる。特に、指定された文中に矛盾しないような論述を完成させる訓練( 記述式問題集などで)が、求められる。
2024年度 県立高校入試問題分析【数学】
| 大問数 | 6問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 寺内大智 |
入試問題分析と講評
大問数は変化なし。出題分野および学習する学年も幅広く構成。全体の難易度は例年通りだが細かな変更点が多くある。思考力と読解力を問う傾向にあるのは近年と同様。基本的な問題も多く出題された一方で比較的難しい問題は面積を比較する問題が多かったのが本年の特徴といえる。
大問別分析
【大問1 】
正負の数、平方根、絶対値、2 次方程式の解、反比例、おうぎ形、球の体積、相対度数からの小問集合。
【大問2 】近似値の範囲・連立方程式・整数の説明
四捨五入した近似値から真の値の範囲を求める問題。道のりと時間に関する連立方程式。連続する3 つの整数の性質を説明する問題で従来の穴埋め形式から部分的な記述式に変更。
【大問3 】角の二等分線の作図・三平方の定理・合同の証明
作図は昨年も用いた角の二等分線が出題。平面図形で三平方の定理から斜辺を求める問題や、面積を比較することで高さを求める問題。三角形の合同の証明が昨年に続き出題され、円周角と平行線の錯角を絡めた問題。経験がないと角度の説明が難しいタイプであった。
【大問4 】ヒストグラムと箱ひげ図・確率
階級値を答える問題、ヒストグラムと箱ひげ図の対応関係を選ぶ問題。確率は( 1 )と( 2 ) で全通り数が異なることに注意が必要だが全通り数は2 5 通りと少なめである。
【大問5 】放物線・1 次関数
放物線で変域を求める問題。比例定数の大小から直線の傾きを語句から選ぶ問題が新傾向。三角形の面積比較は例年同様。
図形の重なる面積をまとめた表を穴埋めさせる問題。グラフの概形を選ぶ問題。面積が同じ値になる時間を求める問題。座標が与えられず自分で計算する必要があるところが変更点である。
図形の重なる面積をまとめた表を穴埋めさせる問題。グラフの概形を選ぶ問題。面積が同じ値になる時間を求める問題。座標が与えられず自分で計算する必要があるところが変更点である。
【大問6 】規則性
新幹線の座席数とタクシーの乗車数から人数を求める問題。最後は変数が2つで答えが1つに決まらないタイプであり、整数の規則の知識も必要である。
新傾向や注意すべき問題
解答記述式の問題が4 題から5 題へ増加。全体の難易度では時間を多く取られる難問や奇問がない点から調整は感じる。しかし、文章量が増え、問題設定も設問ごとに変わることが多いため時間配分に注意。
2025年度入試への対策
問題の内容を素早く正確に読み取り、時間内に解答としてまとめ上げる力が必要となる。日頃から解法の流れやそこに至る過程を理解するようにしましょう。パターンで解くだけでなく思考を巡らせる習慣こそ本番でのパフォーマンスに影響します。一回の授業を大切に!
2024年度 県立高校入試問題分析【理科】
| 大問数 | 9問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 出島亜紀 |
入試問題分析と講評
出題傾向は例年通り、大問1 が小問集合、大問2 から大問9 までは, 物理・化学・生物・地学の4 分野から2 題ずつ, 全3 6 問の出題であった。中1 の内容から2 単元、中2 ・中3 の内容から各3 単元とバランスよく出題された。記述問題は昨年より減少し4 問の出題。同様に計算問題も減少し4 問の出題となった。実験や観察に対しての考察をする問題, 資料やグラフの読み取りの問題が増加した。
大問別分析
各問題は基本的な知識を問う問題と考察問題の組み合わせになっている。大問ごとの分析内容は以下の通りである。
【大問1】<小問集合>
選択4 問、記述4 問と例年通り。基礎的な知識を確かめる問題である。
【大問2】<微生物のはたらき>
微生物のはたらきと生物量ピラミッドに関する問題。草食動物が減少した場合の肉食動物と植物の数量変化を考察する問題が出題された。
【大問3】<電流のはたらき>
オームの法則、電力量等の基礎的な計算問題に加え、家庭用電源の配線を考察する問題が出題された。正確に資料を読み取る力や複雑な回路図を読み取る力が必要。
【大問4】<天気の変化>
天気図の読み取りに関しての出題。複数の資料を基に気象要素( 気温、湿度、気圧の変化) を読み取る力が問われた。
【大問5】<ダニエル電池>
ダニエル電池の基本的な仕組みを理解していれば正答できたと思われる。基本的な問題が中心で、難易度もさほど高くなかった。
【大問6】<地層>
凝灰岩の層の様子から火山の噴火を考察する問題が出題された。複数の資料を読み取らなければならないため, 難易度が高めの問題であった。
【大問7】<植物の分類>
植物の分類に関する基礎的な問題の出題であった。ここはしっかりと得点したいところである。
【大問8】<水圧・浮力>
物体の体積と浮力の関係が理解できていれば、さほど難易度は高くなかった。基本的な問題が中心であった。確実に得点しておきたい。
【大問9】<炭酸水素ナトリウムの分解>
実験の操作方法、化学反応式、未反応の計算が出題。基本的な知識があれば正答できた。未反応の計算は少し難しかった。
新傾向や注意すべき問題
基礎的な問題から新傾向の問題まで幅広く出題されている。そのため、全体的な難易度としてはそれほど高くない。しかし、実験や観察の結果など複数の資料から考察しなければならない問題も一部で出題されおり、これらの問題では読解力や思考力など、総合力が問われている。
2025年度入試への対策
物理・化学・生物・地学の4 分野からバランスよく出題されるため、偏りの出ないよう3 年間の内容を学習していくことが必要である。また、基礎的な知識だけではなく、それらをもとに理論を構築していく力を養っていかなければならない。常日頃から実験や観察に積極的に参加し、結果を分析し、考察していくことを習慣にしていくとよい。
2024年度 県立高校入試問題分析【英語】
| 大問数 | 5問 |
| 試験時間 | 50分 |
| 担当 | 谷田貝友紀 |
入試問題分析と講評
昨年も出題構成が変更されたが、今年も一部に問いの順番や形式の変化が見られた。全体としては中学で学ぶ基礎的・基本的な内容についての出題で、基本的な語い、文法、文構造の理解が必要。「思考力・判断力・表現力」を試す出題といえるので、時間内に要点を把握して英文を読む力や、英語や日本語で解答できる表現力などが必要。
大問別分析
【大問1】英文を聞いて要旨を把握する問題
昨年と同じ形式の問題。英文を聞いて、適する絵や図を選ぶ問いや、英語の対話を聞いて、要点のメモを完成させるために英単語を書く問いが出題された。必要な情報を整理し、話し手が伝えたいことの概要や要点を捉える力が試される。
【大問2】適切な語句を選ぶ問題・整序結合問題・テーマ作文
昨年と出題の順番、形式が変化。
1 は1 0 0 語程度の短い文章を読み、文法や文構造、単語・熟語の知識が問われた。「原形不定詞」、「熟語」、「動詞」、「前置詞」、「副詞」、「動名詞」が出題。
2 は対話形式の整序結合で、「文型」、「進行形」+ 「分詞」、「疑問詞疑問文」が出題。
3 は昨年最後の問いであった、テーマ作文が出題。〔条件〕に従い、5 0 語程度で書かれた相手のメールを読んで、5 文程度の英文を書く問い。
1 は1 0 0 語程度の短い文章を読み、文法や文構造、単語・熟語の知識が問われた。「原形不定詞」、「熟語」、「動詞」、「前置詞」、「副詞」、「動名詞」が出題。
2 は対話形式の整序結合で、「文型」、「進行形」+ 「分詞」、「疑問詞疑問文」が出題。
3 は昨年最後の問いであった、テーマ作文が出題。〔条件〕に従い、5 0 語程度で書かれた相手のメールを読んで、5 文程度の英文を書く問い。
【大問3】説明文
語数は昨年よりやや減少。昨年同様、要旨を把握し、字数制限つきの日本語にまとめる問いが出題。
【大問4】物語文
こちらも語数は昨年よりやや減少。主人公の心情を選ぶ問い、文脈を読み取り、字数制限つきの日本語で答える問い、英語の質問に英語で答える問題や内容一致の問いなどが出題。
【大問5】対話文
こちらも語数は昨年よりやや減少。対話の流れを把握しながら要点を捉える力、対話や図に基づき英文を完成させる力が問われた。
新傾向や注意すべき問題
出題構成が2 年連続で変更された。構成の変化に戸惑わず、時間内に解答を仕上げる力が必要。全体の語数は昨年と比べると減少したが、それでも時間内に解くには練習が必要。英語4 技能「聞く・読む・書く・話す」の向上に努めよう。
2025年度入試への対策
入学試験で合格点を取る「応用」力を身につけるには、「理解」、「定着」が必須。単語のつづりや文法事項を確かめながら、教科書の音読、書き取り練習をくり返そう。英文に慣れて、5 0 分で解答を仕上げられる力を養おう。英検に挑戦したり、土曜ゼミや日曜ゼミなどの入試対策講座に参加したりして、英語の力を向上させよう。Do your best!